
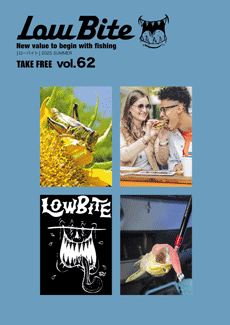
مپ“مپ“èٹ¦مƒژو¹–مپ«مƒ–مƒ©مƒƒم‚¯مƒگم‚¹مپŒهکهœ¨مپ—ن»ٹه¹´مپ§100ه¹´ç›®م‚’è؟ژمپˆمپںم€‚مپمپ—مپ¦è‡ھهˆ†éپ”مپŒç”ںمپ¾م‚Œم‚‹ه‰چمپ‹م‚‰و–‡هŒ–مپ¨مپ—مپ¦و ¹ن»کمپچم€پو°—مپŒمپ¤مپ‘مپ°مƒœم‚¯م‚‰مپ®ه؟ƒمپ§ه®؟م‚‹é‡چè¦پمپھهکهœ¨مپ«مپھمپ£مپ¦مپ„مپںم€‚100ه¹´م‚‚مپ®و™‚مپŒçµŒمپ¦مپ°م€پè‡ھ然界مپ®ç’°ه¢ƒم‚‚ه¤‰م‚ڈم‚ٹم€پوˆ‘م€…مپŒوڑ®م‚‰مپ™ن¸–مپ®ن¸مپ¨مƒ–مƒ©مƒƒم‚¯مƒگم‚¹مپ¨مپ®ن؛‹وƒ…م‚‚ه¤‰م‚ڈمپ£مپںم€‚مپ¨مپ¯è¨€مپˆم€پéپ،م‚Œمپ°مƒœم‚¯م‚‰مپ®هژں点مپŒمپ“مپ“مپ«مپ‚م‚‹مپ“مپ¨مپ«مپ¯é–“éپ•مپ„مپھمپ„م€‚مپم‚“مپھèٹ¦مƒژو¹–مپ¨مپ¯م€پمƒœم‚¯م‚‰مپ«مپ¨مپ£مپ¦èƒ¸è†¨م‚‰م‚€ï¼ˆمƒھم‚¹مƒڑم‚¯مƒˆï¼‰مپ®مپ¯ه½“然م€‚ه؟ƒمپ¨è‚Œمپ§و„ںمپکمپںمپ„8ن؛؛مپŒèٹ¦مƒژو¹–مپ«é›†مپ¾مپ£مپںم€‚
مƒœم‚¯م‚‰ï¼کن؛؛مپŒو€مپ†مƒگم‚¹مƒ•م‚£مƒƒم‚·مƒ³م‚°
Teru(My First Story)
مپھمپ‹مپھمپ‹é‡£م‚Œمپھمپ„مپ‹م‚‰مپ“مپ釣م‚Œمپںو™‚مپ®ه–œمپ³مپŒمƒ‡م‚«مپ„م€پمپ—مپ‹م‚‚مƒ“مƒƒم‚°مƒ™م‚¤مƒˆمپھم‚“مپ¦م€‚و°—وŒپمپ،良مپڈمپ¦مپ‚مپ®ه؟«و¥½مپ‹م‚‰وٹœمپ‘م‚‰م‚Œمپھمپ„م€‚
Kouki(Crawler Boyz)
ن»™هڈ°مپ‹م‚‰و¥مپ¾مپ—مپںمپ‘مپ©م€پمپ“مپ“مپ«ç«‹مپ£مپ¦é‡£م‚ٹم‚’مپ•مپ›مپ¦م‚‚م‚‰مپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ“مپ¨مپ«و„ںè¬مپ—مپںمپ„م€‚100ه¹´مپ®و´هڈ²م‚’و€مپ†مپ¨مƒ‰م‚مƒ‰م‚مپ—مپںم€‚
Tatsuya(Survive Said The Prophet)
مƒگم‚¹مپŒ100ه¹´çµŒمپ£مپ¦م‚‚ه¤–و¥ç¨®و‰±مپ„مپ£مپ¦ن¸چو€è°م€‚وœ€م‚‚ه¤–و¥ç¨®مپ¯م€پمپم‚‚مپم‚‚ه¤§é™¸م‚’و¸،مپ£مپ¦هگ„هœ°م‚’ن¾µç•¥مپ—مپ¦مپچمپںن؛؛é–“مپ‹م‚‚مپ§مپ™مپ(笑)م€‚مپ“مپ®م‚؟م‚¤مƒںمƒ³م‚°مپ§م€پمƒگم‚¹مپ¯وœ¬ه½“مپ«ه°ٹمپ„مپ¨ه†چèھچèکمپ—مپںم€‚
Teru(Lunker Killer)
مپ“مپ®éڑمپ«ن؛؛ç”ںم‚’ه¤‰مپˆم‚‰م‚Œمپ¦مپ—مپ¾مپ£مپں(笑)م€‚م‚‚مپ—ن¸–é–“مپ®é¢¨ه½“مپںم‚ٹمپŒو°—مپ«مپھم‚‹مپ®مپھم‚‰و¢م‚پم‚Œمپ°è‰¯مپ„مپ‘مپ©م€پم‚‚مپ†è‡ھهˆ†مپ¯و¢م‚پم‚‰م‚Œمپھمپ„م€‚
Taro(Electric Japan)
مƒگم‚¹مƒ•م‚£مƒƒم‚·مƒ³م‚°مپ£مپ¦م€پè‡ھ然م‚„ç”ں物مپ¨وœ¬و°—مپ§مپ¶مپ¤مپ‹مپ£مپ¦م‚‹و„ںمپکمپŒوœ€é«کï¼پ
Toshi Koike(Abu Garcia)
مƒگم‚¹مپ¯م‚·مƒ³مƒ—مƒ«مپ«و ¼ه¥½è‰¯مپ„م€‚ç¾ژمپ—مپ„م€‚مƒگم‚¹مƒ•م‚£مƒƒم‚·مƒ³م‚°مپ«ه‡؛ن¼ڑمپ£مپ¦مپ„مپھمپ‹مپ£مپںم‚‰ن»ٹمپ®è‡ھهˆ†مپ¯مپ„مپھمپ„م€‚Respect!
Kawada(Abu Garcia)
هگŒمپکمƒگم‚¹م‚’و„›مپ™م‚‹ن»²é–“مپ«ه‡؛ن¼ڑمپˆمپںمپ“مپ¨مپ¯م€پمƒœم‚¯مپ«مپ¨مپ£مپ¦مپ®è²،産م€‚
Koma 2(Low Biteمƒ»Cokehead Hipsters)
BASSINGمپ¨مپ¯م€Œéڑمپ®هڈ£مپ«é‡م‚’وژ›مپ‘م‚‹مپ مپ‘مپŒé‡£م‚ٹمپکم‚ƒمپھمپ„ï¼پم€چمپ¨مپ„مپ†م€پمƒمƒ¼مƒگم‚¤مƒˆمپ®مƒ¢مƒƒمƒˆمƒ¼مپ¨é‡£م‚ٹمپ®ه¥¥è،Œمپچم‚’و•™مپˆمپ¦مپڈم‚Œمپںم€‚
1925ه¹´م€پو—¥وœ¬مپ«م‚„مپ£مپ¦و¥مپںمƒ–مƒ©مƒƒم‚¯مƒگم‚¹
ه›½ه†…مƒگم‚¹مƒ•م‚£مƒƒم‚·مƒ³م‚°م‚«مƒ«مƒپمƒ£مƒ¼مپ®م‚مƒƒم‚«م‚±م‚’ن½œمپ£مپں赤وکں鉄馬و°ڈمپ¯م€پمپ©م‚“مپھو°—وŒپمپ،مپ§مپ“مپ“èٹ¦مƒژو¹–مپ«مƒ–مƒ©مƒƒم‚¯مƒگم‚¹م‚’و”¾وµپمپ—مپںمپ®مپ م‚چمپ†ï¼ںم‚¢مƒ،مƒھم‚«ç”£مپ®مƒگم‚¹مƒ•م‚£مƒƒم‚·مƒ³م‚°مپŒم€پمپ¾مپ•مپ‹مپ“مپ“مپ¾مپ§وˆ‘م€…و—¥وœ¬ن؛؛مپ®ه؟ƒم‚’وژ´م‚€مپ¨و€مپ£مپںمپ م‚چمپ†مپ‹ï¼ںه½“و™‚مپ®ه؟ƒه¢ƒم‚’وک¯éèپمپ„مپ¦مپ؟مپںمپ„م€‚ه®ںéڑ›مƒگم‚¹مƒ•م‚£مƒƒم‚·مƒ³م‚°مپ«م‚ˆمپ£مپ¦ن؛؛ç”ںم‚’و”¯مپˆم‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹ن؛؛مپŒمپ©م‚Œمپ مپ‘مپ„م‚‹مپ م‚چمپ†مپ‹م€پ赤وکں鉄馬مپ•م‚“مپ«و„ںè¬مپ®è¨€è‘‰م‚’言مپ„مپںمپ„ن؛؛مپ¯ç„،و•°مپ«مپ„م‚‹مپ«éپ•مپ„مپھمپ„م€‚ن»ٹه¹´2025ه¹´م€پم‚‚مپ—م‚؟م‚¤مƒ م‚¹مƒھمƒƒمƒ—مپ§مپچم‚‹مپھم‚‰م€Œمƒ–مƒ©مƒƒم‚¯مƒگم‚¹و¥و—¥100ه‘¨ه¹´مپ®مƒ“مƒƒم‚°مƒ‹مƒ¥مƒ¼م‚¹م€چم‚’ه½¼مپ«و•™مپˆمپ¦مپ‚مپ’مپںمپ„م‚‚مپ®مپ م€‚
2005ه¹´م€پ特ه®ڑه¤–و¥ç”ں物مپ«وŒ‡ه®ڑمپ•م‚Œمپںمƒ–مƒ©مƒƒم‚¯مƒگم‚¹
مƒ–مƒ¼مƒ مپŒو•…مپ‹ï¼ںمپ“مپ®و،ن¾‹مپ®م‚؟مƒ¼م‚²مƒƒمƒˆمپ¨مپ—مپ¦و³¨ç›®م‚’集م‚پم€پن¸€éƒ¨مپ®ه›½ه†…مƒگم‚¹مƒ•م‚£مƒƒم‚·مƒ³م‚°مپ«هژ³مپ—مپ„è¦ڈهˆ¶مپŒç™؛ç”ںمپ—逆風مپ«و™’مپ•م‚Œمپںم€‚مپمپ—مپ¦ن¸–é–“مپ®é¢¨ه½“مپںم‚ٹمپ¯ن¸€و°—مپ«و‚ھهŒ–م€‚و‚ھ者و‰±مپ„م‚’مپ•م‚Œم€پن¸€éƒ¨مپ®ه°ڈه¦و ،مپ§مپ¯ه¤–و¥ç”ں物ï¼ه®³éڑمپ¨مپ„مپ†و•™è‚²مپŒمپھمپ•م‚Œمپںم€‚مپ“مپ®م‚ˆمپ†مپھوƒ…ه‹¢مپ«ç–²م‚Œم€په‚·مپ¤مپچم€پç«؟م‚’ç½®مپ„مپںمƒگم‚¹مƒ•م‚£مƒƒم‚·مƒ£مƒ¼مپ¯ه°‘مپھمپڈمپھمپ„م€‚مپ—مپ‹مپ—مƒگم‚¹مƒ•م‚£مƒƒم‚·مƒ³م‚°مپŒç¦پو¢م‚„éپ•و³•مپ«مپھمپ£مپںم‚ڈمپ‘مپ§مپ¯مپھمپ„م€‚ه¼·مپ„و„ڈه؟—مپ¨é«کمپ„مƒ¢مƒپمƒ™مƒ¼م‚·مƒ§مƒ³ï¼ˆمƒ•م‚£مƒƒم‚·مƒ£مƒ¼مƒمƒ³م‚·مƒƒمƒ—)م‚’وŒپمپ¤مƒگم‚¹مƒ•م‚£مƒƒم‚·مƒ£مƒ¼مپ“مپمپŒن»ٹو—¥مپ¾مپ§م‚«مƒ«مƒپمƒ£مƒ¼م‚’و”¯مپˆç¶ڑمپ‘م€پمپ“مپ®100ه‘¨ه¹´مپ¨مپ„مپ†èھ‡م‚ٹé«کمپ„و—¥م‚’è؟ژمپˆمپںم€‚مپمپ®ه¼·مپ„و„ڈه؟—مپŒم€Œéپٹمپ³م€چمپ¨مپ„مپ†و¦‚ه؟µمپ•مپˆم‚‚飛مپ³è¶ٹمپˆمپ¦م€پمƒگم‚¹مƒ•م‚£مƒƒم‚·مƒ³م‚°م‚«مƒ«مƒپمƒ£مƒ¼مپ¨مپ—مپ¦مپ“مپ“و—¥وœ¬مپ«و ¹ن»کمپ„مپںم€‚
2025ه¹´م€پن»ٹمپھمپٹوˆ‘م€…مپŒو„›مپ—مپ¦و¢مپ¾مپھمپ„مƒ–مƒ©مƒƒم‚¯مƒگم‚¹
ن¸چéپ‡مپھو™‚ن»£م‚’経مپ¦مپچمپںمƒگم‚¹مƒ•م‚£مƒƒم‚·مƒ£مƒ¼مپ‹م‚‰م€پمپمپ®و™‚ن»£مپ«مپ¯è§¦م‚Œمپ¦مپ„مپھمپ„مƒگم‚¹مƒ•م‚£مƒƒم‚·مƒ£مƒ¼مپ¾مپ§م€پمپ¨مپ«مپ‹مپڈمƒگم‚¹مƒ•م‚£مƒƒم‚·مƒ³م‚°مپŒه¥½مپچمپ§م€پمپ“مپ®100ه‘¨ه¹´مپ«و•¬و„ڈمپ¨و„ںè¬م‚’وٹ±مپڈ8ن؛؛مپŒèٹ¦مƒژو¹–مپ«é›†مپ¾مپ£مپںم€‚ç·‘è±ٹمپ‹مپ§è‡ھ然مپ¨ن؛؛é–“مپŒه…±هکمپ—م€پ観ه…‰هœ°مپ¨مپ—مپ¦م‚‚هگچé«کمپ„èٹ¦مƒژو¹–م€‚مپ“مپ®هœ°مپ§م€پهگŒمپکو™‚ن»£م‚’ç”ںمپچوٹœمپ„مپ¦مپچمپں104ه¹´ç›®م‚’è؟ژمپˆم‚‹â€œAbu Garciaâ€مپ®مƒھمƒ¼مƒ«م‚’وڈ،مپ£مپ¦çµ‚و—¥é‡£م‚ٹم‚’و¥½مپ—م‚“مپ م€‚“Abu Garciaâ€مپ¨مپ¯م‚¹م‚¦م‚§مƒ¼مƒ‡مƒ³مپ®م‚؟م‚¯م‚·مƒ¼مƒ،مƒ¼م‚؟مƒ¼م‚’è£½é€ مپ™م‚‹ن¼ڑ社مپ‹م‚‰ه§‹مپ¾مپ£مپں釣ه…·مƒ،مƒ¼م‚«مƒ¼م€‚ن»£è،¨مƒ¨مƒ¼مƒ†مپ•م‚“مپ®é‡£م‚ٹه¥½مپچمپŒé«کمپکمپ¦مƒھمƒ¼مƒ«مپ¨مپ„مپ†é‡چè¦پمپھ釣م‚ٹéپ“ه…·مپ®é–‹ç™؛مپ«è‡³مپ£مپںم‚ˆمپ†مپ م€‚مپ¾مپ•مپ«مƒگم‚¹مƒ•م‚£مƒƒم‚·مƒ³م‚°م‚«مƒ«مƒپمƒ£مƒ¼مپ¨ه…±مپ«و©م‚“مپ§مپچمپںمپ¨è¨€مپ£مپ¦م‚‚éپژ言مپ§مپ¯مپھمپ„م€‚
مپ“مپ®م‚ˆمپ†مپھمپ“مپ¨م‚’胸مپ«ç§کم‚پم€پمƒ–مƒ©مƒƒم‚¯مƒگم‚¹ن¸ٹ陸100ه¹´ç›®م‚’ه؟ƒمپ‹م‚‰ç¥مپ„èٹ¦مƒژو¹–مپ§ç«؟م‚’وŒ¯مپ£مپںم€‚ مپ“مپ®ن¼پç”»مپ«è³›هگŒمپ—مپ¦مپ„مپںمپ مپ„مپںAbu Garciaمپ«و„ںè¬مپ—مپ¾مپ™م€‚
https://www.purefishing.jp/product/brand/abugarcia/